はじめに|光を透す、祈りの模様
ジャーリーパターン。
それは、透かし彫りによって光と風を通す、インド建築特有の装飾です。
壁の一部が、
まるでレースのようにくり抜かれ、
そこに浮かび上がるのは、花のかたち、星のかたち、永遠に続く幾何学。
そのひとつひとつが、
祈りの場を包み、
強い日差しや喧騒をやわらげながら、
静けさと、美しさを内側に生み出していく。
そんなジャーリーの美しさを、
かいらりではアクセサリーという形で、
身近に、やさしく、届けています。
「この模様、なぜか惹かれる」
そう感じたことがある方へ──
この記事では、
ジャーリーパターンの意味と歴史、そして“装飾を超えた力”を、
やさしく紐解いていきます。
ジャーリーパターンとは?|透かしに宿る知恵と美
ジャーリー(Jali)とは、
主にインド・イスラム建築で発達した、装飾的な透かし彫りの格子模様のことです。
石や木、金属などの板に、
幾何学模様や植物文様をくり抜いて作られたパネルで、
窓や壁の一部として建物に組み込まれています。
語源と背景
「ジャーリー(jali)」という言葉は、
ヒンディー語やウルドゥー語で“網”や“格子”を意味し、
その語感どおり、内と外を柔らかく仕切るための構造として用いられてきました。
インドではムガル時代(16~18世紀)にその技術が洗練され、
王宮やモスク、霊廟などの神聖な空間に多用されるようになります。
とくにアクバル帝(1556〜1605年)以降の建築群に見られるジャーリーは、
建築装飾としての完成度が極めて高く、
タージ・マハルやファテープル・シークリーなどにも精緻な格子が残されています。
素材とつくり
伝統的なジャーリーは、
主に以下のような素材で作られます:
- 白大理石・赤砂岩(建築用):神聖さと耐久性を兼ね備えた伝統素材
- 木材:ラージャスターン地方などで、室内仕切りや家具に応用
- 金属(真鍮・銅など):近代以降、インテリアやアクセサリー装飾として展開
とくに石材のジャーリーは、
職人がノミ一本で丁寧に文様を彫り抜いていくものであり、
精緻な職人技の象徴としても知られています。
次のセクションでは、
この模様が建築においてどんな意味を持ち、
どんな役割を果たしていたのかを探っていきましょう。
インド建築におけるジャーリーの役割|光と風を編む構造
ジャーリーは、ただ美しいだけの装飾ではありません。
機能性と精神性を併せ持つ“呼吸する壁”として、建築の中で重要な役割を果たしてきました。
🌞 光を和らげるフィルター
インドの強い日差しを、直接遮るのではなく、
模様越しに柔らかく取り込むことで、
室内に穏やかな明暗のグラデーションを生み出します。
日中でも、直射日光はジャーリーを通して拡散され、
空間の中に“光の文様”が静かに踊る。
タージ・マハル(アーグラ)やスーフィー霊廟の内部では、
幾何学模様の影が床や壁に投げかけられ、時間の移ろいさえも可視化します。
🌬️ 風を通す、呼吸する壁
ジャーリーのもうひとつの機能は、通気性です。
細かな透かしが風の流れをゆるやかに通し、
閉ざされた空間に自然な涼しさを届けます。
とくに砂漠地帯のラージャスターン地方では、
アンベール城(ジャイプール)やハヴェーリー(伝統邸宅)などの建築に、
この機能的な装飾が巧みに取り入れられてきました。
🪶 内と外を隔て、つなぐ
ジャーリーの格子は、視線を遮りながらも、
外の光や気配を室内に残す“半透明の境界”。
外からは見えにくく、内からはやわらかく世界を感じることができる──
女性の居室(ゼナーナ)や礼拝空間の仕切りとしても用いられ、
「守られた内側」と「開かれた外側」を繋ぐ精神的な装置でもありました。
このように、ジャーリーは構造・装飾・象徴を一体化させた、
インド建築ならではの“知恵の結晶”です。
次のセクションでは、
その模様が持つバリエーションや意味について、もう少し掘り下げていきましょう。
モチーフのバリエーションと意味|繰り返しの中にある祈り
ジャーリーの模様は、単なる装飾ではありません。
繰り返しの中に祈りが宿るとされるその意匠には、
古くから人々の信仰、宇宙観、そして日常の願いが込められてきました。
✴️幾何学模様|永遠と秩序の象徴
もっともよく見られるのが、対称性のある幾何学模様です。
六角形・星形・格子・螺旋──
これらはイスラム建築の精神とも関わる、終わりのない連続性=永遠性を示しています。
幾何学は、宇宙の秩序や神の法則と重ねられ、
「人が手を加えられる美」の極致として、高度な職人技術で作られてきました。
🌿植物・花のモチーフ|生命の循環と豊かさ
蓮、蔓草、花輪、パルメット(椰子葉)などの植物モチーフもよく使われます。
これらは生命力や再生、繁栄を象徴する意匠であり、
礼拝所・王宮・墓廟など、時間と向き合う空間に静かに寄り添ってきました。
とくに蓮はインドでは聖なる花とされ、
内なる浄化と精神性の象徴として多く用いられています。
🌌星と花が重なる模様|宇宙と心の交差点
ジャーリーではしばしば、花弁のような星や、星形の中心に花が咲くような構図が見られます。
これは宇宙(星)と人間の心(花)が重なり合う意匠として解釈され、
まるで建物そのものが“内なる宇宙”を映し出しているようです。
反復する星型模様は、ただの美しさを超えて、
「整ったものの中にある感情」のような不思議な余韻を残します。
次のセクションでは、
こうした模様たちが、どのようにアクセサリーとして息づいているか──
かいらりのジャーリーパターン商品とともにご紹介します。
かいらりとジャーリーパターンアクセサリー|手のひらに、建築の詩を
かいらりでも、このジャーリーパターンを取り入れたアクセサリーを多数ご紹介しています。
手のひらサイズの世界に、建築の静けさと光のリズムを詰めこんだような──
そんなデザインたちです。
🌿 こんな方におすすめ
- 凛としたエスニック感がほしい
- 透け感のあるモチーフで余白を楽しみたい
- 建築的・抽象的な美しさに惹かれる
ジャーリーパターンは、
“見せる”のではなく“透かす”ことで魅せるデザイン。
肌にのせたとき、そこに光と空気の余白が生まれます。
🛍️ ジャーリーパターンアクセサリー一覧はこちら
まとめ|透かし模様に込められた静かな願い
ジャーリーパターンは、
ただの装飾でも、建築技法でもありません。
それは、光と風を通しながら、祈りや暮らしを包む、静かな装置。
幾何学の秩序、植物の生命力、宇宙のかたち。
そのすべてを、静かに、けれど確かに、語り続けています。
目立たず、騒がず、
けれど心にふと残る、その「透けた存在感」。
建物の一部として
日常の空気の中にあるからこそ──
この模様には、“続いていく願い”のようなものが宿っているのかもしれません。
アクセサリーとして、
ふと手にとったときにも、
そのひと粒の奥に、
誰かの時間や、祈りの断片が息づいています。
もし、何かに惹かれるようにこの模様を選んだなら──
それはきっと、あなたの中にも「透かし模様」があるから。






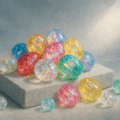

コメント